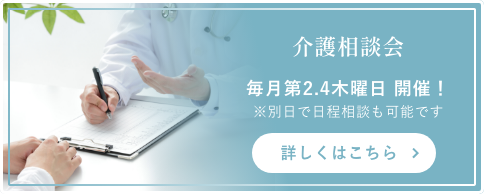安全に美味しく食べるための取り組み
生活の中で「食べること」は不可欠であり、大きな楽しみでもあります。そのため当施設では、「安全においしく食べるための取り組み」に力を入れています。
取り組みの1つとして、看護師、介護福祉士、理学療法士、作業療法士、歯科衛生士、管理栄養士からなる嚥下チームが活動しています。嚥下チームは月に1度ミーティングを行ない、咀嚼・嚥下に課題がある方の食事の見直しや、職員に向けた勉強会の開催を行っています。
ご利用者様の摂食・嚥下機能に応じて、安全においしく食事を召し上がっていただけるよう、各職種が協力して取り組んでいます。

入所時の安全においしく食べるための取り組み
- 入所時の嚥下機能評価:コップ一杯ほどのお水を飲んでいただき、飲み込む力を確認します。
- むせはないか
- 飲み込む際に喉仏がしっかり上がっているか
- 水分が喉に引っかかっていないか
- 飲んだ後にガラガラ声になっていないか
- とろみ剤は必要か
- とろみの強さはどの位がよいか
医師や看護師、管理栄養士は、今まで食べていた食形態(柔らかさ、形、量など)を確認します。
- 口腔内の状況の確認
歯科衛生士が、お口の中の状況を確認します。
- 唇の状態(色、乾燥はないか)
- 舌や歯肉、粘膜の状態(乾燥や異常、汚れはないか)
- 唾液の状態(潤いがあるか、べたつきがないか) 歯の状態(虫歯や破折はなか)
- 義歯の状態(合っているか、正しく使えているか)
- 歯磨きの状態(磨き残し・歯石・口臭はないか)
- 口の中に痛みがないか
- 食形態の決定
これらの情報を組み合わせて、はじめに提供するお食事の形態を決めています。
当施設の食形態は、下記の通りです。
《当施設の食形態》
主食の種類:米飯、軟飯、全粥、ミキサー粥
副食の種類:常菜、軟菜、一口大(常菜・軟菜)、きざみ、きざみあんかけ、ソフト、ペースト
⼊所中の安全においしく⾷べるための取り組み
食形態は一度決めたら変更しないというわけではなく、ご利用者様の状態に合わせて日々調整しています。
ご利用者様の状態の把握は多職種で行っています。
管理栄養士が食事中に行うミールラウンド、看護師・介護福祉士が行う介食事介助や口腔ケアの際、下記のような点を気にかけています。

食事の場面
- 食事姿勢(極端に体が傾いていないか、深く座れているか等)
- どんな食べ方をしているか(ご飯/おかずのみいつも食べている、○○を残されている等)
- 一口で口の中に入れる量は適切か、極端な早食いになっていないか
- 食べづらいものはないか
- むせはないか(むせている場合、何でむせているか)

口腔ケアの場面
- 歯磨きの際、口の中に食べかすが多く残っていないか
(食べかすが多く残っている場合、その場所はどこか) - 義歯は合っているか、正しく使えているか
- 舌や歯肉、粘膜の汚れはないか
- うがいができるか
- 口腔体操・発声練習
食事の前に口腔体操や発声練習を取り入れ、安全においしく食べるための支援をしています。
- 食事の姿勢・ポジショニング・自助具
安全に食事を食べるためには、食事時の姿勢も重要です。
姿勢に課題があるご利用者様には理学療法士・作業療法士が介入し、その方にあった食事姿勢がとれるよう調整しています。
普通の食器や食具での食事が難しい方に対しては、自助食器や自助食具を提案する場合もあります。
こうした取り組みを通して、なるべくご自身で食べられるような環境づくりを目指しています。
「安全においしく食べる」ためには、様々なポイントがあります。
そうしたポイントを多職種で観察・対応を検討し、よりよい入所生活が送れるよう支援してまいります。